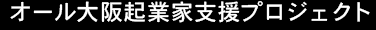大阪の起業家
毎日5分おしゃべりするだけ!めんどくさいを解消した健康管理 AIアプリ『otomo』

デイジーヘルステック株式会社 代表取締役CEO
佐々木 峻介 氏
私は「人を幸せにする仕事がしたい」との想いで理学療法士となり、病院で患者様と向き合う日々を送っていました。でも、現実は、予防医療を促進させることの方が大切であり、促進させたいと思っていました。そこで今回着目したのは、睡眠、食事、体調管理といった日々の生活をサポートするアプリです。既に多くの生活習慣改善アプリがあるものの、多くの方がアプリ活用を継続できていません。理由は「めんどくさい」です。その理由は、「入力がめんどくさい」「厳しい食事制限や運動を強いられめんどくさい」などです。そこで開発したのが、会話型AIヘルスケアパートナー『otomo』。毎日5分、スマホに向かって今日の出来事や食べたものや一日の行動についておしゃべりするだけ。おしゃべりからキーワードとなるデータを抽出し、食事や健康管理を自動で記録、ライフスタイル・趣味嗜好を理解した上で、認知行動療法に基づいて一人ひとりに最適なサポートを提案します。仕事で疲れてお菓子を食べてしまった時も、otomoが共感で支えてくれます。otomoは、一人ひとりの日常に寄り添うAIパートナーがいる世界を創ります。そして、心も体も自分らしく健康でいられる毎日を提供します。
HP:https://daysy-healthtech.com/
- 起業家紹介
佐々木 峻介(ささき しゅんすけ) デイジーヘルステック株式会社 代表取締役CEO
北海道出身。医療系大学卒業後、理学療法士として神奈川県の総合病院に勤務。
若くして寝たきりになる患者とその家族を前に、現場では「病気になる前に支える手段」がなく、無力感を痛感した。医療現場の限界を越えて社会全体に予防医療を届けるため、IT業界に転身。フェンリル株式会社などで7年間、開発とPjMを経験し、直近ではAIスタートアップで生成AIを用いたtoB会話型AIエージェントや会議・インタビューデータ分析プロダクトのPdM・開発を担当。
2024年10月、生成AIプロダクトの開発力と医療の知見を生かし多くの人に予防医療を届けるべくデイジーヘルステック株式会社を創業。
- 起業のきっかけ
私は理学療法士として、総合病院で多くの患者様と向き合ってきました。
しかし、現場で目にしたのは「病気になってからでは救えない」現実でした。若くして寝たきりになる患者様や、そのご家族の苦しみを何度も目の当たりにし、「このまま診療の現場だけでは救える人が限られてしまう」と強い無力感を感じました。
生活習慣病や不調は自己責任論に押し付けられ、健康支援の仕組みは十分に届いていません。
「そもそも予防行動が続けられない人を、どうやって支えるか」。これが私の原体験から生まれた問いです。
同時に、私が大学生の頃からデジタルヘルスの進展やAI活用による行動変容支援の有効性が、次々と論文や事例で報告され始めていました。私は、テクノロジーの力と医療を掛け合わせれば事業性と健康的インパクトを両立した形で予防医療を届けることができるポテンシャルがあると考えたことがきっかけでした。
- 起業までの道のり
私はテクノロジーの力と医療を掛け合わせれば事業性と健康的インパクトを両立した形で予防医療を届けることができるポテンシャルに気付き病院を離れ、IT領域にキャリアチェンジしました。
フェンリル株式会社をはじめ、開発やプロジェクトマネジメントを7年間経験し、技術とサービス開発を学びました。
直近では、AIスタートアップAlenxにて会話型AIエージェントやミーティング・ユーザーインタビュー分析プロダクトの開発・PdMも担当し、生成AIを用いたプロダクト開発の知見や開発力を積みました。
この経験から、「今まで解決できなかった課題を、生成AIと医療の知見を掛け合わせれば突破できる」と確信。
「続けられない人にこそ健康を届ける」その仕組みをつくるため、2024年10月、デイジーヘルステック株式会社を創業しました。
- 今後の思い
今、私たちのサービスは少しづつですが、確実にユーザーに愛されている手応えを感じています。
実際に使ってくれている方から、喜んでいただけている声も届いており本当に嬉しいことです。
小さいかもしれませんが、確実に健康的な変化が生まれ始めています。
今後は、さらに一人ひとりの行動や感情・生活に深く寄り添えるプロダクトへと磨き込み、サポートの質を上げていきます。
その延長線上で、アクティブシニアや遠隔地の高齢者、または専門的なサポートが必要な層にも対応できるよう専門家やパートナーと連携した機能拡張など、一人一人のパートナーとしてより効果的な存在として、そしてより大きな事業インパクト・ヘルスケアインパクトを提供していくロードマップを描いています。私たちは「単なるアプリ」に留まるつもりはありません。スタートアップが歩むべき小さな一歩目として、個人のダイエット・健康習慣の継続支援からスタートしつつ、人と人、人と地域が繋がる新しいヘルスケアインフラの基盤を作ることをめざしています。
- 支援機関名