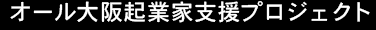起業・経営お役立ち記事
ローカル・ゼブラ企業に学ぶ~社会課題を解決!『社会貢献ビジネス』のつくり方」~

<異世界アニメのお約束>
異世界ものというアニメのジャンルは、毎年一定数の新しい作品が登場する分野に成長してきました。異世界に転生するというコンテンツは、私の記憶では1983年にも「聖戦士ダンバイン」という作品があったので、古くからあった物語テーマです。最近はファンタジーゲームなどとともに異世界のイメージが共有され幅広い作品で使われています。
異世界の住人として登場するのが、魔法使いやエルフ、ドワーフ、ホビット、亜人などといった様々な人種設定があり、それぞれの特徴を踏まえた仲間づくりや活躍もあり物語の魅力にも繋がっています。
昨年放送された「ダンジョン飯」もその一つです。協力しながらダンジョン攻略をするストーリですが、自分のスキルや役割を踏まえパーティーに協力する姿勢は「社会貢献ビジネス」にもみられる光景です。
最近は、社長と社員という組織の枠組みだけでなく、仲間とともに社会貢献ビジネスを目指す方も増えてきております。ここでは、社会貢献ビジネスの具体的な事例を踏まえ、事業モデルの検討ポイントをご紹介していきます。
<海外の事例「ゼブラ企業とは?」>
ゼブラ企業とは、2017年に、アメリカで始まった社会課題の解決と持続可能な経営の両立をめざす企業の概念です。成長(市場の独占)と拡大(上場の時価総額)をめざすユニコーン企業が称賛される社会の流れに危機感を抱いた4人の女性起業家が提唱し、メディアで紹介されるようになりました。
日本では、2024年3月1日に中小企業庁から策定公表された「地域課題解決事業推進に向けた基本指針」(※1)で、自治体の支援の在り方と伴に、先行するゼブラ企業の事例が紹介されています。
例えば、規格外の農作物を新たな規格で流通させ、地元農家の所得向上や女性の健康問題に取り組む福島県の「株式会社 陽と人(ヒトビト)」、林業の6次産業化とローカルベンチャーの創発を進める岡山県の「株式会社 エーゼログループ」などが紹介されています。
(※1)中小企業庁:地域課題解決事業推進に向けた基本指針(PDF)
<社会貢献事業のアイデアはどこから生まれる?>
事業アイデアをどのように思いついたのかを仕組みとして説明することはできません。ただ、ほとんどの社会貢献ビジネスが、自身の体験と接点があります。インターネットの成功事例の記事から読み取れるのは「美味しい地域なのに、あまり知られていないのはなぜ」といった仕事上で触れ合った素朴な疑問が発端です。
先に紹介した「株式会社 陽と人」は、ホームページに「民間企業に転職し、地域活性化に関わるコンサルティングを行う中で、改めて福島県とのご縁に恵まれた。」とあり、事業活動をとおして地域資源の魅力に気が付いたことから“地域商社”の設立に至ったことが書かれています。
中小企業庁が紹介している事例は、成功事例です。どの地域でも同じようにいくわけではありませんが、「何か大きなことをしたい」というより、「隣人の困りごとを解決したい」という視点で考えると、誰にでも事業のチャンスが生まれてきます。例えば、日常の「不便・不満」、隣人の困りごと(家族やご近所づきあい)、地域の困りごとなどです。これらを起点に、情報収集と仲間を探します。情報収集や仲間づくりには、コワーキングスペース、ネットを活用した活動の情報発信、起業支援施設などいろんな場が存在していますので、これらを活用して自分のビジネスモデルを検討していきます。
<事業として成立するための検討ポイント>
社会貢献ビジネスで起業する場合も、その他の分野での起業と同様、継続的な活動をしていくためには利益獲得が課題となります。社会貢献ビジネスのビジネスモデルを作成する際のポイントをまとめると、①課題の“当事者性”とニーズの明確化、②“稼ぐ方法”の設計、③スモールスタート、④共感できるビジョン設定、⑤地域との関係性構築、⑥社会的インパクトの可視化などがあげられます。
①課題の“当事者性”とニーズの明確化
誰のどんな課題を解決するのか。その課題に自身が関わってきた実感はあるかについて明確にしていきます。明確化する理由は他者に説明して、共感を得るためです。
②“稼ぐ方法”の設計
誰がお金を払うのかをしっかり考えます。課題解決に経済的価値を見出せるか客観的に見つめます。とくに社会貢献ビジネスでは補助金頼みになっているケースもありますが、補助金は予算状況によりなくなるケースもあるので、補助金に頼らない持続可能なビジネスにするための稼ぐ方法は必須です。
③スモールスタート
仮説を立てて検証できるルートを探します。仮説というと大げさですが、市民マルシェやレンタルスペースでのデモンストレーションなどを活用して、実際の声を聞くことが大事です。
④共感できるビジョン設定
参加者(協力者、利用者など)を増やすには、共感できるビジョンとそれを実践している姿勢が求められます。特に立場が変われば目的も利害も異なる参加者に関わってもらいます。
⑤地域との関係性構築
ゼロから始めるよりは、地域の集まりらを活用し始められるところから小さく始め、自分が関われる事業領域を広げていきます。とはいえ、“コワーキングの利用者”、“地域コミュニティの地域住民”、“行政・既存団体”は目的も利害も異なるケースがほとんどです。「何をともに作る」「どう一緒に育てる」といった共感できるポイントを探し戦略的に関わり方を決めていきましょう。
⑥社会インパクトの可視化
決算数値とは別に社会インパクトを数値で示していきます。社会貢献ビジネスでは、地域での多様性の実現などの課題に取り組むケースもあると思いますが、できる限り数値化で社会的インパクトを捉えることができるようにします。例えば、多様性であれば、女性、外国人や障がい者の活躍の場や人数などを数値化するなどです。
数値化するだけでなく、丁寧な説明が求められるので決算説明と同様に、事業がどんなインパクトを社会に創出し、今後どうなっていくのかなどを発信していくことも求められます。
<事業活動のファンをつくる>
社会貢献ビジネスがめざす「持続可能性」や「多様性への取り組み」はZ世代が関心を寄せています。こうした世代に取り組みたい企業にとっても、ファンを増やす重要な要素となります。多様性に柔軟な姿勢は、厳しい経営環境の中でも支持され、社会的なインパクトを生む事業として期待されています。
- 公開日
- 2025年4月16日
- 執筆者
大西 森(おおにし しげる)氏
大阪産業創造館 経営相談室 スタッフコンサルタント
中小企業診断士